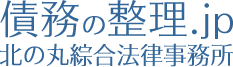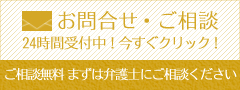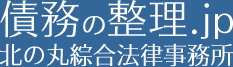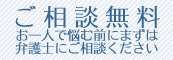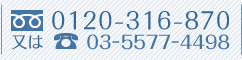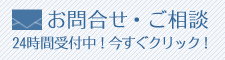- ホーム
- 過払金返還請求の歴史
過払金返還請求の歴史
過払金返還請求のはじまりとは?
現在では、当たり前におこなっている過払金返還請求ですが、もちろんはじめから認められていたわけではありません。
下に挙げた判例等の蓄積によって、過払金の返還請求ができるようになったのです。
昭和39年11月18日最高裁判決
昭和43年10月29日最高裁判決
昭和43年11月13日最高裁判決
昭和39年11月18日最高裁判決の解説
現在、債務整理等をする場合、まずは貸金業者から開示された取引履歴を利息制限法に基づいて引き直し計算を行います。その際、利息制限法の制限超過部分を都度元本に充当して債務残高を算出するという手法が広く用いられています。この引き直し計算は、昭和39年11月18日最高裁判決に根拠があるのです。
つまり、この最高裁判決は、利息制限法所定の制限利率を超える利息や損害金の元本充当を認め、これまでの判例の解釈を大きく変更しました。この判決がなければ、後に過払金返還請求が認められるということもなかったでしょう。そういった意味で、大変重要な判決と言われています。
昭和39年11月18日最高裁判決は、これまでの判例解釈を変更し、以下の判断をしました。
『債務者が、利息制限法(以下、「本法」とする)所定の制限を超える金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払ったときは、右制限をこえる部分は民法491条により残元本に充当されるものと解するを相当とする。(中略)
債務者が利息、損害金の弁済として支払った制限超過部分は、強行法規である本法1条・4条の各1項により無効とされ、その部分の債務は存在しないのであるから、その部分に対する支払いは弁済の効力を生じない。従って、債務者が利息、損害金と指定して支払っても、制限超過部分に対する指定は無意味であり、結局その部分に対する指定がないのと同一であるから、元本が残存するときは、民法491条の適用により、これに充当させるものと言わなければならない。
本法1条・4条の各2項は、債務者において、制限超過部分を任意に支払ったときは、その返還を請求することができない旨規定しているが、それは、制限超過の利息・損害金を支払った債務者に対し裁判所がその返還につき助力を与えないとした趣旨と解するを相当とする。(中略)
さらに、債務者が任意に支払った制限超過部分は残存元本に充当されるものと解することは、経済的弱者の地位にある債務者の保護を主たる目的とする本法の立法趣旨に合致するものである。右の解釈のもとでは、元本債権の残存する債務者とその残存しない債務者の間に不均衡を生ずることを免れないとしても、それを理由として元本債権の残存する債務者の保護を放擲※するような解釈をすることは、本法の立法精神に反するものといわなければならない。』
※放擲・・・自分のなすべきことをしないで放っておくこと
まず、この当時の利息制限法1条2項、4条2項には、
「債務者が同法所定の利率を超えて利息・損害金を任意に支払ったときは、その超過部分の返還を請求することができない」
という規定、つまり、自分の意思で利息制限法所定の制限利率を超える利息や損害金を支払った以上は、もはやその部分の返還を求めることはできないという規定がありました(現在では既に削除されています)。
この規定に沿って考えると、超過部分の返還を請求できなくなるということは、その支払った制限超過利息は債権者のものということになり、制限超過部分を残債務の元本に充当することはできないということになります。現に、この最高裁判決以前の判例では、制限超過部分の元本への充当は認められないと判断されていました。
ところが、このような考えでは、経済的弱者である債務者の保護を主な目的として、利息の利率を制限する利息制限法の立法趣旨に反することになってしまいます。
そこで、最高裁はこれまでの解釈を変更し、当時の利息制限法1条・4条の各2項は、あくまで返還請求ができなくなるというだけに過ぎず、制限超過部分を元本に充当することもできなくなるという意味ではないと判断しました。
この判決により、利息制限法所定の制限利率を超える利息を支払った場合、その制限超過部分は債務の元本に充当されることが明らかになりました。
昭和43年10月9日最高裁判決の解説
前掲の昭和39年11月18日最高裁判決により、制限超過部分が元本に充当されることは明らかになりましたが、貸金業者と借主との間に弁済の充当合意がある場合に、どのように取り扱うべきかということについてまでは判断されていませんでした。
今日、貸金業者から開示された取引履歴を利息制限法に基づいて引き直し計算する際に、貸金業者と借主との間の充当合意の内容は、ほとんど気にせず計算を行います。それは、昭和43年10月9日最高裁判決に根拠があるのです。
昭和43年10月9日最高裁判決は、以下のとおり、当事者間の充当合意は無効になると判断しました。
『金銭を目的とする消費貸借上の債務者が、利息制限法所定の制限をこえる利息、損害金を任意に支払ったときは、右制限をこえる部分は強行法規である同法1条、4条の各1項によって無効とされ、その部分の債務は存在しないのであるから、その部分に対する支払いは弁済の効力を生じないものである。したがって、本件のように数口の貸金債権が存在し、その弁済の充当の順序について当事者間に特約が存在する場合においては、右債務の存在しない制限超過部分に対する充当の合意は無意味で、その部分の合意は存在しないことになるから、右超過部分に対する弁済は、充当の特約の趣旨に従って次順位に充当されるべき債務であって有効に存在するものに充当されることになるものと解すべきである。(中略)
本件において、原審は、当事者の主張に基づき、本件貸金債権を含む上告人の被上告人に対する3口の貸金債権の約定利息の利率はすべて利息制限法所定の制限をこえていること、被抗告人から上告人に対する弁済金の支払いはすべて任意になされたこと、上告人と被上告人との間には弁済の充当の順序について原判示の特約が存在すること、を確定したのであるから、被上告人の特別な主張をまつまでもなく、被上告人から支払われた弁済金については、右特約の趣旨に従って、利息制限法所定の範囲内で、順次、利息、遅延損害金の弁済に充当されたうえ、その余は当該債務の元本に充当されたものとした原判決の判断は正当である。したがって、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。』
まず、弁済の充当とは、借主が貸金業者に対して支払った金銭を、元本・利息・遅延損害金・費用等のどれに支払ったことにするかということで、充当の順番については、当事者間で決めてよいことになっています。
ここで問題になるのは、当事者間で充当の順番を決めていた場合に、制限超過部分は、元本ではなく、約定で定めた順番のもの(利息、遅延損害金等)に充当されることになるのか、という点です。
仮に、元本ではなく、約定で定めた順番のものに充当することが認められると、利息制限法の制限超過部分は元本に充当されるとした前掲の昭和39年11月8日最高裁判決が無意味になってしまうおそれがあります。
そこで、最高裁は、制限超過部分は無効であり、その部分の債務は存在しないのだから、その存在しない制限超過部分に弁済を充当するという合意は無意味であり、仮に、当事者間に弁済充当の合意があったとしても、効力を生ずるのは利息制限法に違反しない限度にすぎないから、制限超過部分は、弁済充当の合意に従って、利息制限法に違反せずに無効とならない部分に充当されていくにすぎないと判断しました。
この判決により、当事者間に弁済の充当合意があった場合の充当方法が明確になり、過払金返還請求に一歩近づいたように思います。
昭和43年11月13日最高裁判決の解説
昭和43年11月13日最高裁判決は、消費者保護のために敢えてなされた画期的な判決と言われています。
というのも、この最高裁判決以前にも、利息制限法の制限超過部分は無効であり、支払済みの制限超過部分は元本に充当されるとした昭和39年11月18日最高裁判決や、当事者間に弁済の充当合意がある場合にどのように取り扱うかについて判断した昭和43年10月29日最高裁判決等は、存在していました。
しかし、制限超過部分を、いわゆる「過払金」として借主に返還しなければならないとする判例はありませんでした。
これは、この当時の利息制限法1条2項、4条2項に、
「債務者が同法所定の利率を超えて利息・損害金を任意に支払ったときは、その超過部分の返還を請求することができない」
という規定、つまり、自分の意思で利息制限法所定の制限利率を超える利息や損害金を支払った以上は、もはやその部分の返還を求めることはできないという規定があったからです(現在では既に削除されています)。
このような状況下で、昭和43年11月13日最高裁判決は、同規定を維持しつつ、以下の判断をしました。
『債務者が利息制限法所定の制限をこえて任意に利息・損害金の支払を継続し、その制限超過部分を元本に充当すると、計算上元本が完済となったとき、その後に支払われた金額は、債務が存在しないのにその弁済として支払われたものに外ならないから、この場合には、利息制限法の法条の適用はなく、民法の規定するところにより、不当利得の返還を請求することができるものと解するのが相当である。』
当時の利息制限法1条・4条の各2項の規定は、金銭を目的とする消費貸借について元本債権が存在することを当然の前提とするものであり、元本がなくなった状態では規定が適用されない、というのが最高裁の解釈です。
ですから、元本がなくなった後にした弁済は無効となり、債務がないのに(法律上の原因がないのに)金銭を受け取っていたということになるので、貸金業者に対し、不当利得として返還請求できるのです。この最高裁判決によって、はじめて過払金返還請求ができる、ということが確定したのです。